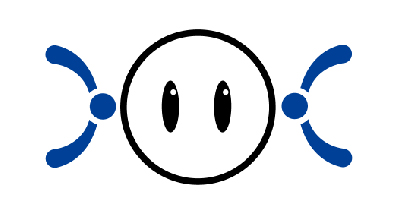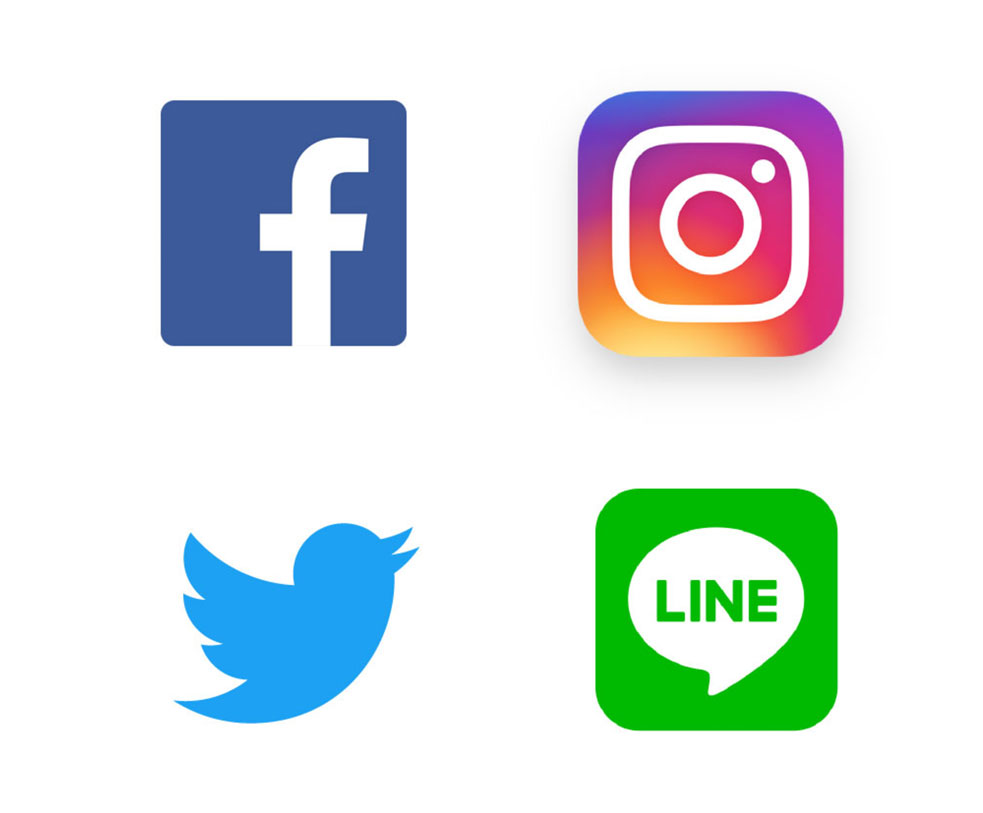【2025年最新】SNSマーケティングとは?効果を上げるコツや主要SNSの特徴を解説
- 投稿日 :
- カテゴリー : Instagram, SNSの基本

非常に多くの人が使用しているSNSは、個人間同士の交流ツールだけに留まらず、企業のマーケティングツールとしても活用が進んでいます。Webマーケティングと言えば、運用型広告やSEO対策などが挙げられますが、SNSマーケティングは新たな柱として定着しつつあります。
当記事では、これからSNSマーケティングを取り組む方や、SNSマーケティングについてもっと深く知りたいという方に対して、網羅的に解説していきます。
Contents
SNSマーケティングとは?
SNSマーケティングとは、InstagramやLINE、TikTokにXなど、ソーシャルネットワークサービス(SNS)を活用してマーケティング活動を行うことです。
SNSはプライベート利用が多く全ての人が投稿できるため、口コミによる情報の拡散が起こりやすいツールです。適切に利用することで、認知度を高めることやコミュニティを形成することでファン化に繋がります。
最近では、サービス・商品の紹介だけでなく、外国の方に対する観光誘致や、自社の採用活動、IR活動などさまざまな方面で活用が進んでいます。
SNSマーケティングは、顧客とのコミュニケーションができる
従来のマーケティングや、何かの媒体に広告を掲載することや、SEO対策としてブログやコンテンツの掲載、イベントの開催などを行って認知を上げていくことが一般的です。どれも、企業が主体となって何らかのメッセージを伝えることで、認知とブランド力を向上させて、購買行動などに繋げる「一方通行」での施策です。
SNSの最大の特長は「双方向性」があるため、顧客と直接関係性を築けることです。フォトコンテストなど投稿企画を通じてコミュニケーションを取ることや、自社の商品・サービスに対する投稿にコメントができます。顧客が抱えている不満を早期にキャッチアップすることや、評価されている点を見つけ、さらなる改善を行うことができます。
双方向のコミュニケーションを通じて、ファン化に繋げることができれば、さらなる口コミによる新規顧客の獲得につなげることができます。
SNSマーケティングの重要性が高まっている2つの理由
SNSの利用率は、8割を超えるほど多い
総務省が掲載している「令和5年通信利用動向調査の結果」によると、日本国内においてSNSの利用率は80%を超えます。さらに13歳~30歳においては90% を超え、59歳までにおいて80%を超します。
SNSは、人々の生活に必要なツールの1つになっています。マーケティング活動においては、なるべく顧客の多い所に対して対策を行っていくことが重要であるため、SNSはマーケティング活動においても非常に重要なツールと言えます。
SNSで調べ物をするユーザーが増えている
同じく、総務省の調査を見ると、SNSの利用目的では「知りたいことについて情報を探すため」が第2位で63.4%もの人が該当しています。
以前までは、コミュニケーションや自分の投稿などが中心でしたが、昨今では情報収集のツールとして利用されています。顧客となり得るターゲットが、自社商品・サービスに近しい情報収集を行った時に、適切にリーチができるようSNSマーケティングを行っていくことは非常に重要です。
SNSマーケティングの効果とメリットとは?
利用者が多い中、ターゲティングが出来る
SNSマーケティングでは、投稿を行い認知拡大することに加え、広告を出すことができます。広告に関しては、各SNSごとに細かいターゲティング設定ができます。例えば、Instagramでは年齢性別に加え、仕事や学歴・ライフイベントなどカテゴリに分けた設定が行えます。ピンポイントで狙いたい層に対して広告を訴求することができます。
通常の投稿によるマーケティング活動においても、ハッシュタグなどの機能により主にターゲットにしたい層を絞ることができます。利用者数が多く且つ、細かいターゲティングができるため、効率的にターゲットへの認知向上に繋げることができます。
口コミを増やして、認知拡大を行える
人は身近な人の意見に影響される傾向があります。以前までは芸能人など知名度の高い人に多くの人たちが影響されていましたが、趣味趣向が多様化している現代においては、SNS上で一般ユーザーが投稿した内容に影響されるケースも増えてきています。
SNSマーケティングにより、自社の商品・サービスに関する投稿を促すことや、SNSユーザーが拡散したくなるような投稿を行うことで、効率的に口コミを増やしていくことができます。
半分以上が一般の人の投稿で購入に至る調査結果も
当社の親会社である「ユミルリンク株式会社」では、2024年11月に「SNSフォローやメルマガ登録のきっかけにおける実態調査」を行いました。
そこで、全国20歳以上の男女1299人に、「企業主体の投稿以外(ユーザーの口コミなど)で購入に至った方は、 どんな人による投稿がきっかけで購入をしたか教えてください。 ※複数回答可」と質問をしたところ以下の結果になりました。
| 芸能人の投稿 | 21.0% |
|---|---|
| インフルエンサー(企業提携)の投稿 | 36.8% |
| インフルエンサーのオススメ | 34.0% |
| 一般の方の投稿 | 49.6% |
| 友人の投稿 | 10.9% |
| その他 | 10.2% |
芸能人や友人の投稿よりも、一般の方の投稿が多く50%近い状況に。
出典:【Cuenoteサイト】メルマガ・SNSユーザー実態調査
ファン化やコミュニティを作り、LTVを最大化することができる
SNSは、双方向性があるため、投稿コンテンツを通じてコミュニティを作りファン化することができます。
SNS上の投稿を通じて認知してもらい、定期的な投稿により興味関心を高め、直接の接点などによりファン化に繋がります。ファン化することで、商品の好意度が増し、選ばれる確率が高まるため、LTVを上げることができます。
さらに、ファンとなったユーザーの中には、積極的に商品・サービスを広める人もいるため、新たな新規顧客の獲得にも結びつきます。
顧客のニーズやインサイトを知ることができる
SNSマーケティングは、顧客や未顧客の投稿も見ることができます。商品・サービスの良い感想があれば、ご指摘頂く投稿もあります。これは、「なぜ選んでいただいたのか」「なぜ選ばれなかったのか」など顧客のニーズやインサイトを知るきっかけになります。
企業としてSNS運用のハードルが高い場合には、SNSの投稿調査から始めてもよいでしょう。
SNSマーケティングでの注意点とデメリット
炎上リスクが伴う
「炎上」という言葉をよく耳にする昨今。企業がコンテンツを発信していく過程において炎上するリスクはあります。特に人の価値基準はそれぞれ異なります。
特に悪い口コミは良い口コミよりも素早く広まる可能性があります。炎上しないよう政治などの話題や特定の人・モノを下げる内容など、炎上に繋がりかねない内容の投稿は避けるようにしましょう。
また万が一炎上してしまった場合の対応策も事前に決めておくと良いでしょう。
直接的な購買行動には紐づきにくい
SNSの投稿をみて、サイトに訪れて購入や申込などを行うことは多くはありません。SNSの投稿を見て興味関心が高まり、第一想起されやすい状況にあるうえで、ニーズが発生したタイミングで購入・申込などに繋がります。
そのため、売上に対する効果測定がしにくい特徴があります。SNSの特徴と役割を十分理解したうえで、UGCの投稿数など間接的な部分での効果も確認しましょう。
運用に負担がかかる
特にInstagramやTikTokなどの写真・動画を伴ったSNSは、投稿するためのコンテンツ作りを行う必要があり、運用の負担がかかります。SNS運用を開始したばかりの場合では、結果が見えるフォロワー数もなかなか増えないため、辛抱強く運用していくことが大切です。
一方、一定数のフォロワーが増えていくと、口コミや拡散もされやすくなるため、効果も出やすくなります。
SNSマーケティングの代表的な5つの手法
SNSの自社アカウント運用
SNSマーケティングの基本として「自社アカウントの運用」があります。主に自社コンテンツを投稿していくことです。投稿には、直接商品を宣伝する方法だけでなく、例えば暑いグラウンドに清涼飲料水の商品を置いた写真を置くなど間接的に投稿したり、調味料を販売している企業では、その調味料を使ったレシピの投稿など、情報を届ける投稿にはさまざまあります。
また、投稿についたコメントに対して返信を行って、顧客とコミュニケーションを図ることもあります。
SNS広告
SNS広告は、各媒体の各所に目立つように画像や動画などのコンテンツを表示することができるものです。基本的に運用型広告と呼ばれ、広告費と配信する場所、そしてターゲットなどを自ら設定して配信します。
比較的少額から運用できるため、アカウントを立ち上げたばかりの時にアカウントへの認知度を早期に高めることや、フォトコンテストなどユーザーの投稿を促すイベントなどにおいても有効です。
インフルエンサーマーケティング
インフルエンサーとは、多くの人に影響力のある人を指します。インフルエンサーが商品やサービスを紹介すると、そのフォロワーの人たちに強い影響を及ぼし、購買行動に繋がります。
趣味嗜好が多種多様な現在、SNSでは1万人~数万人のフォロワーがいる「マイクロインフルエンサー」や、フォロワー数が数千人規模の「ナノインフルエンサー」など、非常に多くのSNSユーザーがインフルエンサーになっている時代です。特にニッチな業界に対して精通しているインフルエンサーも数多くいるため、企業側はどのような人と連携していくのか戦略を立てることが重要になっています。
また、企業から依頼して紹介してもらうためには、ステルスマーケティングにならないよう広告であることが分かるように記載する必要があります。
ソーシャルリスニング
SNSを通じて自社サービスに関連する投稿を確認して、品質改善などに繋げていくことです。例えば、自社のファンである人が離反しそうなコメントが増えている場合には、何か顧客満足度低下につながっている可能性があります。
早期にキャッチアップして品質改善を行うことや、SNS上で丁寧に返事を行うことで、ファン化に繋げることもできます。
UGC活用
UGCとは、User Generated Contentの頭文字を取ったもので「ユーザー生成コンテンツ」を指します。SNSにおけるユーザーの投稿がまさにUGCです。
UGC活用は、まさにユーザーの投稿を活用してマーケティング活動に役立てることを指します。例えば、商品にまつわる写真を投稿してもらう「フォトコンテスト」などを開催して、投稿を促します。投稿された写真をサイト上に掲載することや、SNS上で紹介することで新たなファンの獲得に繋げます。
SNSマーケティングの代表的なツール(プラットフォーム)
SNSは複数あるため、SNSマーケティングを行うためには、ツールの選定も重要です。ここではそれぞれの特徴を解説していきますので、選定の参考にしてください。
ただし、1つに絞る必要はありません。例えばショート動画では、InstagramやTikTokなど複数のツールがあります。運用の方針に沿って検討しましょう。
X(旧:Twitter)
旧TwitterであるXは、短い文章をベースにコミュニケーションを行うツールです。リポストと呼ばれる他者の投稿を共有する機能や、トレンドのワードをランキング形式で表示する機能など、拡散力に優れたSNSです。
文章以外にも4枚までの画像や短い動画も投稿することが可能です。
文章ベースのため、一般の人も投稿しやすく、ソーシャルリスニングやUGC活用にも優れています。
Facebookは実名登録制のSNSで世界最大規模のSNSです。一方、日本国内においては、SNSの中では利用率が低く、ビジネスパーソンが多い傾向にあります。そのため、法人向けのビジネスと相性の良いSNSです。また、ターゲティングの精度に優れており、学歴・職業などでターゲティングにも優れています。
Instagramは、「インスタ映え」が有名である通り、画像投稿が中心のSNSです。ショート動画を上げることやライブ配信なども行えます。画像も1度にスライド形式で複数投稿できることから、「キレイな写真」の投稿だけでなく、ノウハウの提供など活用方法は多岐に渡っています。
画像ベースであっても伝わる情報が多いことから、マーケティングツールとしても非常に有効です。一方、Xのようなシェア機能はないため、他のSNSと比べて拡散力はやや弱い傾向にあります。
LINE
LINEは、友人や家族など身近な人との連絡が主となるクローズド要素の強いSNSです。マーケティング活動としても企業アカウントを顧客から友達登録してもらうことで繋がり、メルマガのように情報を届けることができます。
近年では、「VOOM」と呼ばれるショート動画の投稿もでき、他の人と繋がることができるようになったことや、ニュース情報を受け取ることができるなど、機能の幅が広がっています。
TikTok
TikTokは10代、20代など若い人の利用が極めて多いSNSです。ショート動画に特化したSNSで、音楽に合わせて踊った投稿や、料理のコツなど役立つコンテンツ・面白い動画など、多種多様な動画が公開されています。
レコメンド機能が優れていることから、1回の利用の中でも沢山の動画を見る傾向にあるため、再生数が増えやすい傾向にあります。
YouTube
YouTubeはSNSより「動画プラットフォーム」としてのイメージが強いことでしょう。数時間レベルの動画を上げるができるため、他のSNSに比べてより深い情報提供ができます。昨今ではテレビ上でもYouTubeを閲覧できるようになっていることや、他のSNSのようにショート動画の投稿もでき、インフルエンサーによる紹介の影響が大きく表れやすい傾向にあります。
一方、YouTube単独での拡散はしにくく、他のSNSと合わせて運用していくことも重要です。
SNSマーケティングの始め方
SNSは誰でも簡単に始められますが、ただ投稿しているだけで成果に結びつけることは非常に難しいでしょう。成果を伴う運用を行うには、以下の順番に検討しましょう。
SNSマーケティングの目的を明確にする
まずはSNSマーケティングを行う目的を明確にしましょう。
特にSNSはフォロワー数が目につきます。目的を見失うと、フォロワー数を増やすことが目的となり、商品・サービスとは関係のない投稿が増えてしまうケースもあります。
目的の部分では、以下のような例があります。
- 売上を上げる → SNS経由での売上の変化
- 認知を上げる → リーチ数・閲覧数などが指標
- 採用力強化 → 応募数〇%アップ、採用率アップ
フォロワー数を増やすことは、結果的に売上やブランド認知など目的に貢献する可能性がありますが、因果関係があるわけではないため、1つの指標としてみる必要があります。
ペルソナ設定を行う
マーケティングにおけるペルソナとは、狙うべきターゲットの人物像を具体化するために、典型的な顧客像を作成します。
年齢、性別などはもちろんのこと、趣味・嗜好、ライフスタイルなどさまざまな観点で具体的な顧客像を作成します。
「10代の人」へのプレゼントを考えるよりも、「友達の〇〇さん」へのプレゼントを考えるほうがイメージしやすいように、ペルソナを設定することで、届けるべきコンテンツが明確になります。
ペルソナのデメリットとして、実在しない人物像ができてしまう可能性があるため、実際の顧客を分析して作成していくと良いでしょう。
利用するSNSを選ぶ
決めた目的を効率的に達成するために、ターゲットに対してよりブランド訴求できるツールを選びましょう。例えば、コンサルなど無形商材を提供している場合には、文章中心のXや、情報を伝えやすいショート動画があっている可能性があります。
飲食店や観光地など、視覚的訴求が適しているものはInstagramやYouTubeなども適しているでしょう。
運用するSNSは1つに絞る必要はありません。ショート動画であれば、多くのSNSで投稿できるため使い回しができます。メインのSNSを選びつつ、同時に他のSNSにも投稿を行うのもオススメです。
また、YouTubeやInstagramからLINEの友達登録を促すなど、SNSからSNSに遷移させることもできます。
投稿方針を決める
SNSを実際に運用する前に、投稿方針を決めましょう。
特に最初に検討しておくべきポイントは、フォローバックをするか、DMやコメントに対して返信するか、炎上した場合の対応の流れなど、SNSアカウントに対して何かあった時の対応です。その他にも、投稿するコンテンツや頻度、そして内容の方針も検討しましょう。
投稿する「中の人」のキャラクターを決めるのもオススメ!
企業が運営するSNSにおいて、投稿する人のキャラクターを決めることで、親しみやすさを表現することができます。マスコットのようなキャラクターが投稿しているような演出や、広報担当〇〇のように具体的な人柄をアピールしても良いでしょう。
合わせて、発信の口調をですます調にするかなど、キャラクターに合わせた表現の仕方も決めると良いでしょう。SNS運用担当者が変わった場合にもキャラクターが統一されていれば、フォロワーの人が感じる違和感を最小限に抑えることができます。
SNSマーケティングで成果を上げるポイント
参考となるアカウントを見つけて、似せてみる
著作権や企業の立ち位置としてのラインは最低限守る必要がある前提ですが、既にうまくいっているアカウントを見つけて参考にするとよいでしょう。
特に、SNSには流行りの投稿があります。本来のSNS運用の目的から逸脱しないようにしつつも、流行りに合わせた投稿を行うことで、効率的に多くの人にリーチができます。
またアカウントプロフィールの記載の仕方、タグ付けの仕方など細かい所も参考になります。
定期的に各SNSをチェックし、特性を掴む
SNSは、日々目まぐるしく機能が変わっていきます。そしてSNSごとに拡散される仕組みや仕様が変わります。
例えば、Xでいえばトレンドワードを含めた投稿を行うことで表示回数は増えます。Instagramでは以前、ハッシュタグをたくさんつけることで表示回数が増えるようなこともありましたが、昨今ではハッシュタグをつけなくてもInstagram内の検索に引っかかるようになっているため、拡散目的でのハッシュタグの重要性は減っています。
常日頃SNSをチェックし、どのような投稿をすることで目的を達成できるのか情報収集を行いましょう。
顧客のニーズをしっかり把握したうえで運用する
投稿は顧客のニーズにあった訴求をしていく必要があります。例えば、調味料を扱った企業の場合、SNSで顧客が見たいニーズは、調味料の素晴らしさよりも、調味料を使うことで簡単に、おいしい料理が出来るなど、使用後に得られる効果である可能性があります。
ニーズを捉えることは非常に重要です。
採用活動でSNSを運用する場合には、どんな会社なのかという一般的なニーズはもちろんのこと、「どんな人たちがどのように働いているのか」なども気になります。
求人では伝えきれない、従業員の人柄や雰囲気を伝えられるような投稿を行うことで、より会社の魅力を伝えることができ、ミスマッチを防げるため離職率の低下につながります。
広告運用では、PDCAを回す仕組みが重要
SNSの広告は運用型であるため、運用者である企業側での改善が必要です。運用型広告では、主にアプローチするターゲットと入札戦略、そして表示する広告(クリエイティブ)が大きく左右します。
それぞれ、定量的なデータを元に、PDCAを回して改善することが重要です。PDCAを回していくためには、月1回分析して案を検討するなど、予めスケジュールを決めておくなど継続的に行える仕組化が重要です。
SNSマーケティングのよくある疑問
SNSは面白いコンテンツを作らないとダメ?
SNSで、面白いコンテンツ、いわゆるバズるようなコンテンツは必要ありません。
企業のSNSは最終的に売上に繋げることが目的であり、フォロワー数を増やすのではなく、ターゲットに対して正しく訴求しブランディングやファン化に繋げることが大切です。
もちろん、そのなかでバズる面白いコンテンツができれば理想ですが、狙う必要はありません。
フォローバックはするべきなのか?
ブランディングの観点で必要がある時に行うべきでしょう。
フォローバックは、相手に対して好意的・特別感を与えることができますが、フォローバックの主な目的は、相互フォローすることでフォロワー数を増やすことになります。フォローバック目的のフォロワーが増えることや、フォローバックされない人が疎外感を覚えるなどマイナスの影響もあります。
ブランディングの観点からフォローすることが良い場合にのみ、フォローバックを行うとよいでしょう。
DMやコメントは返すべきなのか?
基本的には返したほうがよいでしょう。企業の公式アカウントから直接返事が来るということは、VIP感を与えることや身近に感じてもらいやすくなり、ファン化に繋げることができます。
SNS運用に自信がない場合は、運用を委託することもオススメ
SNSマーケティングは、コツと炎上などの対策、そして情報のキャッチアップなど行うべきポイントが多々あります。特に運用初期やうまくいっていない時には、SNS運用会社に委託して、早期に軌道に乗せることをオススメします。
当社ROCも、これまでの運用実績は500社以上あり、様々な業種業態の企業様のSNS運用を行っています。SNSマーケティングにお困りの方はぜひお問合せください。
SNS運用のプロも使うレポートを自動作成できるツール
「Reposta」

InstagramやFacebookの詳細なレポートを自動作成できるレポートツール「Reposta」。弊社を含むSNS運用のプロも、このレポートを使ってクライアントへ報告を行っています。 レポートの自動作成機能に加え、競合分析機能や、適切なハッシュタグがわかるハッシュタグ分析機能も搭載。 "なんとなく運用"を卒業し、数値に基づいた分析で、アカウントを改善していきましょう! 14日間の無料トライアルをご用意しておりますので、ぜひ実際にお試しください。
SNSマーケティングのプロが実践するInstagram活用術のハンドブックを、
今だけ無料で配布しています!
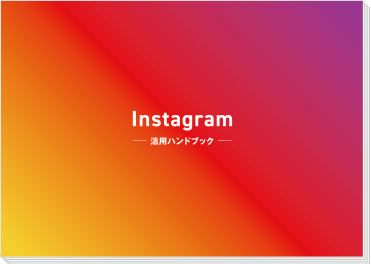
「投稿のポイント」「ハッシュタグのつけ方」「写真撮影法」「Instagramキャンペーン事例」「Instagram広告のポイント」「ショッピング機能について」など・・・。
SNSマーケティングを得意とする株式会社ROCの中でも、入社したディレクターに一番最初に学んでもらう、Instagram活用に欠かせない基本ノウハウを一つの資料にまとめました。
企業のブランディングや集客に必須となっているInstagram。
ぜひこの機会にご確認ください。